「副業をしている場合、開業届を出した方がいいの?」
「開業届を出すメリット・デメリットを詳しく知りたい」
副業で得た収入から経費を引いて20万円以下の場合は「雑所得」となり、確定申告の必要はありません。
ただ、副業で20万円を超える場合や毎月安定した収入を得られるようになったら開業届を出すことでさまざまなメリットがあります。しかし、副業で開業届を出すメリット・デメリットがわからず、本当に出すべきなのかわからない方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では副業で開業届を出すメリット・デメリットについて解説します。おすすめの開業届サービスの紹介をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。この記事を読むことで副業で開業届を出す、出さないの判断ができるようになりますよ。
■この記事は以下の内容が書かれています
- 副業で開業届を出すメリット・デメリットの紹介
- 会社員が副業で開業届を出すには?
- おすすめの開業届サービスの紹介
■この記事でわかること
- 開業届を出すと受けられるお得な情報を知れる
- 開業届を簡単に行えるツールがわかる
- 開業届を出すか悩んでいる人はどうすればいいか解決することができる
それでは、早速スタートします!
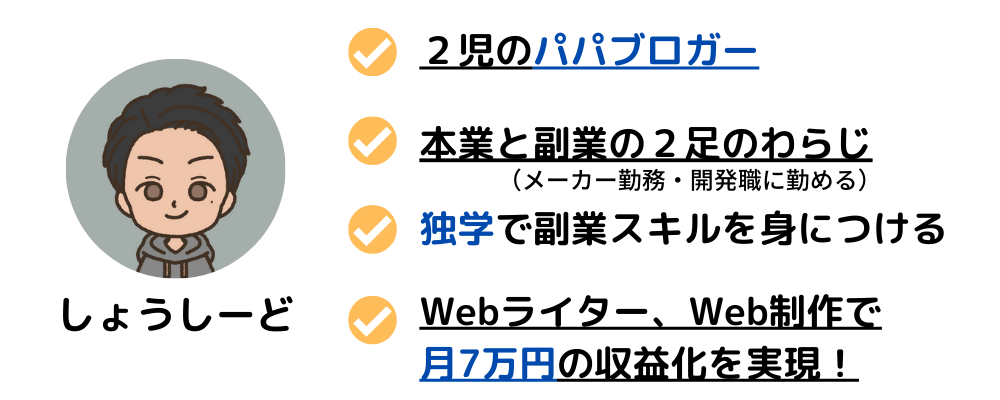
そもそも開業届とは?
まずここでは、副業を始めようとしている人に向けて、開業届について解説をしていきます。
- 開業届の正式名称と法律上の位置づけは?
- 副業サラリーマンも提出が必要なの?
- 開業届の提出は義務か任意か?
開業届を提出すれば、事業の証明などに活用でき、銀行口座の開設・クレジットカードの契約・オフィスの賃貸借契約などに開業届の控えを求められることがあるため、提出しておきましょう。
開業届の正式名称と法律上の位置づけは?
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
これは所得税法第229条に基づいて定められた届出書類で、個人が新たに事業を開始するときに税務署へ提出する重要な書類です。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、法律上、この届出は事業開始から1か月以内に提出することが義務付けられているので、事業を開始した場合は、忘れずに提出をしましょう。
開業届を提出することで、税務上「個人事業主」として認識され、事業所得として所得を申告する必要が生じます。また、この届出により青色申告承認申請書の提出も可能になり、税制上の優遇措置を受けられるようになります。
副業サラリーマンも提出が必要なの?
副業を行っているサラリーマンであっても、継続的に事業として収入を得ている場合は開業届の提出対象となります。
- 投資用に賃貸物件を複数所有している
- 会社とは別にWebライティングやWeb制作の仕事を継続的に行っている
- オンライン講師で毎週講義を行っている
重要なのは「事業性」があるかどうかです。単発のアルバイトや一時的な収入ではなく、継続的・反復的に行っている活動で事業所得として扱われる場合です。たとえば、定期的なブログ収入、副業としての継続的な受注、ハンドメイド商品の販売などは事業に該当します。
ただし、年末調整を受けている給与所得者の場合、副業所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、開業届の提出義務自体は収入額に関係なく発生します。
開業届の提出は義務か任意か?
法的には開業届の提出は義務とされていますが、実際には提出しなかった場合の罰則は設けられていません。
所得税法では事業開始から1か月以内の提出が求められていますが、提出しなくても直接的な不利益はありません。しかし、開業届を提出することで得られるメリットは多く、特に青色申告による65万円の特別控除を受けるためには開業届の提出が前提条件となります。
また、小規模企業共済への加入や事業用銀行口座の開設なども開業届があることでスムーズに進められます。長期的に副業を続ける予定がある場合は、提出しておくことが賢明でしょう。
副業で開業届を出すメリット
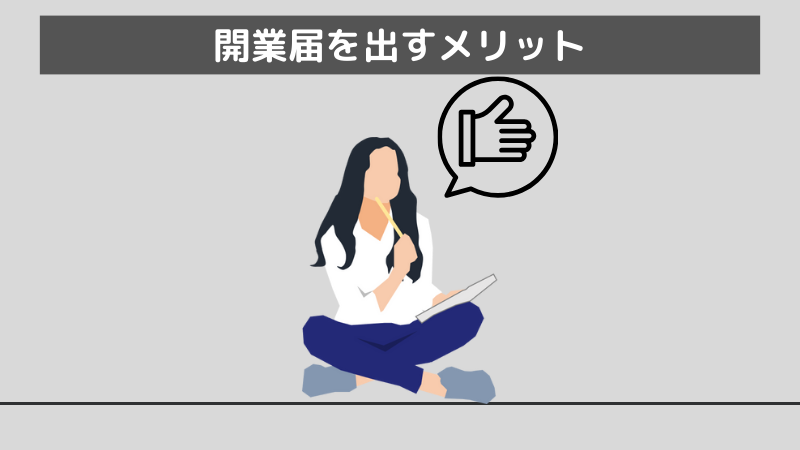
それでは早速、副業で開業届を出すメリットについて解説をしていきます。
- 青色申告特別控除(電子申告なら65万円分)などの節税効果が得られる
- 経費の範囲が広がる
- 助成金・補助金を得られやすくなる
- 損失の繰り越しができる
青色申告特別控除(電子申告なら65万円分)などの節税効果が得られる
青色申告を提出すれば、最高55万円分(電子申告なら65万円分)を所得から控除できるため、節税効果が得られます。
所得金額から差し引かれ課税対象となる金額を安くすることができれば、所得税や住民税を大幅に節税することもできるでしょう。
開業届を出すのは面倒だとよく耳にしますが、開業届をだすことで、お金に関するお得な特典が得られるほかその他にも節税対策として様々あるので、開業届を出すメリットは大いにあります。
経費の範囲が広がる
事業所得も雑所得も経費の範囲としてはほぼ同じ考えですが、異なる部分もあります。
例えば、先ほどもあげたように生計を同じにしている親族や配偶者に支払う給与を経費として計上できることです。
通常、身内への給与は経費にできませんが、事業所得であれば、青色申告で届出をすれば、支払った額を青色事業専従者給与として経費にできます。
なお、以下の条件を満たしている必要があるため対応をしておきましょう。
- 青色事業専従者に支払う給与であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 届出書に記載されている方法、金額の範囲内で支払われていること
- 給与の額が労務の対価としてふさわしいこと
詳細は国税庁のホームページを参考にしてみてください。
参考先:国税庁 │ No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
助成金・補助金を得られやすくなる
開業届を提出し個人事業主になった方は、国や自治体が行っている以下の補助金や助成金、金融機関等の融資を受けられるようになります。
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 創業に関する助成金・補助金
小規模事業者持続化補助金は店舗改装費やチラシ作成費、広告掲載費などを対象に補助額がもらえるもので補助額の上限は50万円、補助率は3分の2まで補助してもらえる。
IT導入補助金は中小企業や小規模事業者が申請可能な補助金となっておりソフトウェアの導入費用などを対象に「A類型」と「B類型」に分かれ、A類型の補助額は30万~150万円未満、B類型の補助額は150万~450万円以下となっています。
最後に創業に関する助成金・補助金は地方自治体や行政機関が用意している補助金制度で副業に活用されるケースが多いです。
賃借料や広告費、教育費などが対象で助成率は経費の3分の2以内、補助額は100万〜300万円まで補償をしてくれます。
損失の繰り越しができる
事業が必ずうまくいくとは限りません。時には失敗をすることもあります。そのため、青色申告をしていれば、損益通算でも事業所得などの赤字があったとき、赤字分を3年間繰越せます。
特に開業したばかりの時期は経営が不安定で、収入も安定せず苦しい時期があると思います。そんなときでも開業届の提出して、青色申告を済ませていれば、赤字を繰り越して事業を続けることができます。
最大3年という制限は付いていますが、赤字のリスクが高い個人事業主にとってこれはかなり大きなメリットではないでしょうか。
副業で開業届を出すデメリット
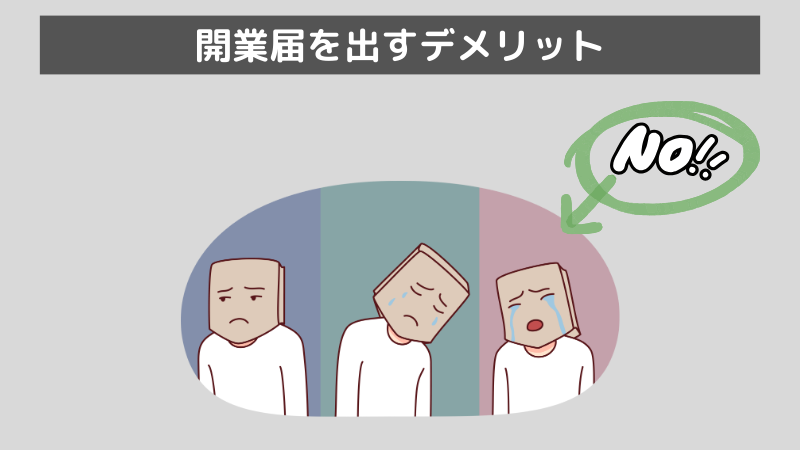
次に副業で開業届を出すデメリットについて、以下3つを詳しく解説していきます。
- 失業手当がもらえない
- 青色申告の手続きが面倒
- 扶養から外れる場合がある
失業手当がもらえない
開業届を出すと、その人は失業者ではなく個人事業主として扱われます。そのため会社を辞めても副業でおこなっている個人事業主の収入があると判断されるため失業手当をもらうことができません。
雇用保険制度では、会社の離職から過去2年間のうち一定期間であれば、基本手当を受給できるようになっていて、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした保険なので、副業で個人事業主としておこなっていれば失業手当の支給対象にならないからです。
仮に会社を辞める予定などある場合は、辞めて失業手当を受け取ってから、開業届を提出した方がよいでしょう。
開業届を提出したのに失業保険を受けると、不正受給として扱われる可能性が高いです。失業手当は不要で個人事業主として収入が充分あるのであれば開業届を早めに出す事も可能です。
青色申告の手続きが面倒
青色申告は節税対策としてメリットが大きいですが、手続きがとても面倒です。
開業届を提出することによって、青色申告で確定申告ができるようになります。先ほど、メリットの部分で記述しましたが、税制上の優遇が受けられる青色申告は、複式簿記などの会計処理、書類の準備が必要です。
最近では、インターネット上で手続きが行えて、負担は軽減されてきましたが、あまり、経理や書類手続きに時間を使いたくない場合には、負担が大きいと感じてしまうかもしれません。
最近ではWeb上で確定申告ができるツールが増えてきていますので、このようなサービスを利用することで確定申告にかかる時間を軽減することができるでしょう。
扶養から外れる場合がある
配偶者の健康保険の被扶養者になっている場合、開業届を出すと被扶養者から外れてしまう可能性があるので注意が必要です。
よく収入などで扶養に入っている、入っていないといった話題になりますが、扶養は以下の分類に分けられます。
- 税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
税法上の扶養は、扶養者(配偶者・子供)の所得が一定額以下であれば開業届の有無に関係なく対象となります。
一方、問題となりやすいのが、健康保険上の扶養です。健康保険上の扶養に入ると、自分で健康保険の保険料を支払わなくても配偶者の会社の健康保険に加入する事ができます。
しかし、この扶養の対象となる人は、各健康保険組合によって決められています。
多くの場合は、扶養に入れるかどうかは収入で判断されますが、開業届を出した個人事業主だと扶養に入れない可能性があります。
もしも、現在扶養に入っていてこれから開業届を出そうと考えている場合には、加入している健康保険組合のルールを事前にチェックしておくことをおすすめします。
副業をしていて開業届を出したほうがいい人・出さなくてもいい人の違い
すべての副業をしている人が、開業届を提出しなければいけないかというと、そうではありません。開業届の提出が必要な人には条件があります。
- 開業届を出した方がいい人
- 開業届を出さなくてもいい人
ここでは、開業届を出した方がいい人と出さなくてもいい人の特徴などを解説していきます。
開業届を出した方がいい人
開業届を出すべき人の特徴として、まず年間所得が、継続的に20万円を超える見込みがある人です。
青色申告による65万円の特別控除を活用することで、大幅な節税効果が期待できるためです。それほかにも、以下にあてはまる人は開業届を提出した方がいい人です。
- 事業として長期的に継続する意思がある人
- 事業用の銀行口座を開設したい人
- 小規模企業共済に加入して退職金の準備をしたい人
このよう人は開業届を提出するメリットがたくさんあります。そのほかにも、フリーランスとして継続的に受注がある場合や、ネットショップ・ブログ運営で安定収入がある場合も該当します。
家族を専従者として雇用し専従者給与を支払いたい場合や将来的に法人化を検討している場合も、開業届の提出が基盤作りとして重要になります。
開業届を出さなくてもいい人
開業届を出さなくても問題ない人は、副業収入が年間20万円未満で今後も大幅な増加が見込めない人です。
この場合、確定申告自体が不要なため、開業届による節税メリットを享受できません。また、単発的・一時的な収入で事業性が低い場合、例えば不用品販売やたまに行うアルバイト程度であれば提出の必要性は低いでしょう。
さらに、会社の副業禁止規定が厳しく、開業届の提出により副業が発覚するリスクを避けたい人も慎重に検討すべきです。ただし、収入が少なくても継続的に事業を行っている場合は法的には提出義務があることを理解しておく必要があります。事業の将来性や規模を総合的に判断して開業届を提出するか決定しましょう。
副業をする会社員が副業届を提出する3つの方法
副業で開業届を提出する人でも、本業で開業届を提出する人でも記入する書類に違いはありません。
どちらも、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の必要な欄を埋めて、開業から1カ月以内に所轄の税務署長に提出します。
開業届の記入方法については以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

税務署で提出する方法
税務署に直接提出する場合は以下の流れで進めていきます。
- 国税庁公式サイトより開業届をダウンロードする
- 必要事項を記入する
- 税務署へ提出をする
まず、所轄の税務署を国税庁ホームページで確認し、開庁時間(平日8時30分~17時)内に訪問します。必要書類は以下です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードがあれば不要)
- 印鑑
- 所得税の青色申告承認申請書
開業届は税務署で入手するか、国税庁ホームページからダウンロードできます。記入項目には氏名、住所、事業内容、開業日、所得の種類などがあり、不明点は窓口で相談可能です。提出時に控えをもらうことを忘れずに。
青色申告を希望する場合は、同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。受付印が押された控えは重要書類として大切に保管してください。
郵送で提出する方法
税務署に行き、必要書類を提出するのは時間に制約がある会社員にとって不便ですよね。それを解消してくれるのが郵送で提出する方法です。
- 必要書類を準備する
- 郵送する(時間外収受箱への投函でもOK)
必要な書類は税務署に提出するときと同じです。ひとつ違うのが、受領印の押された控えを返送してもらうための封筒を準備することです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードがあれば不要)
- 印鑑
- 所得税の青色申告承認申請書
- 返信用封筒
国税庁ホームページから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードし、必要事項を記入します。提出書類は開業届の正本・控え各1部、マイナンバーが記載された本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの両面コピーまたは通知カード+運転免許証など)です。マイナンバーカードや運転免許証などの書類をコピーしたものを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けて提出をしましょう。
控えの返送を希望する場合は返信用封筒(宛先記入・切手貼付済み)を同封します。所轄税務署の住所を確認し、「個人課税部門」宛てに簡易書留で郵送するのが安全です。
青色申告承認申請書も同時に郵送可能で、事業開始から2か月以内(その年の3月15日まで)に提出すれば当年から適用されます。
e-Taxで提出する方法
国税庁による電子申告・納税システムであるe-Taxを利用すれば24時間受付可能です。
- 利用者識別番号を取得する
- 電子証明書を取得する
- e-Taxをインストールする
- 「所得税」を追加する
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択する
- 必要項目を入力する
- 電子署名を付与して送信する
利用には事前準備が必要で、マイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン、e-Tax用のID・パスワードが必要です。
まず国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「開業・廃業等届出書」を選択します。画面の指示に従って必要事項を入力し、電子署名を行って送信します。提出後は受信通知により提出完了を確認できます。e-Taxなら控えも電子データとして保存され、紛失の心配がありません。青色申告承認申請書も同様に電子申告可能です。
初回利用時はマイナンバーカードの設定など準備に時間がかかりますが、一度設定すれば今後の確定申告も電子で完結できる利便性があります。
開業届けが簡単にできるオススメのツールをご紹介!

ここからは開業届け提出できるツールとして、以下4つがあります。
それぞれの特徴などを交えてご紹介しますので自分にあったツールを見つけてみて下さい。
\開業届を提出するなら利用したいツール3選!/
 マネーフォワードクラウド開業届 |  freee開業 | 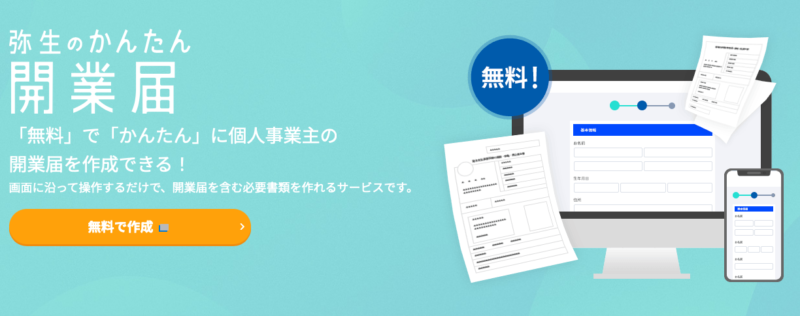 弥生のかんたん開業届 | |
|---|---|---|---|
| 作成時間 | 約10分 | 約5分 | 約15分 |
| 電子申告 | なし | あり | なし |
| 作成書類 | 開業届 青色申告承認申請書 | 開業届 青色申告承認申請書 給与支払事務所等開設届出書 | 開業届 青色申告承認申請書 |
| 会計ソフト連携 | マネーフォワード会計 | freee会計 | 弥生会計 |
マネーフォワードクラウド開業届

マネーフォワードクラウド開業届は株式会社マネーフォワードが運営していて、所得税の青色申告承認申請書など、個人事業主の開業手続きに必要な書類を、web上で無料で作成できるサービスです。
その他にも、家計簿アプリで有名なマネーフォワードMEやマネーフォワード勤怠などの様々なサービスも提供しています。
利用したい方は、フォームに沿って必要事項の入力を進めるだけで、専門知識がなくても自身が提出すべき書類の作成や提出場所の確認ができるため、簡単に手続きを進めることができます。
- 質問に答える
- フォームに沿って必要な情報を入力する
- 作成した資料を税務署に提出をする
上記のように3つのステップで開業届を提出する事ができるのでとてもたすかりますよね。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 作成時間 | 約10分 |
| 操作性 | ★★★★☆ |
| 作成書類 | 開業届・青色申告承認申請書 |
| サポート | メール |
| 会計ソフト連携 | マネーフォワード会計 |
| スマホ対応 | あり |
弥生のかんたん開業届
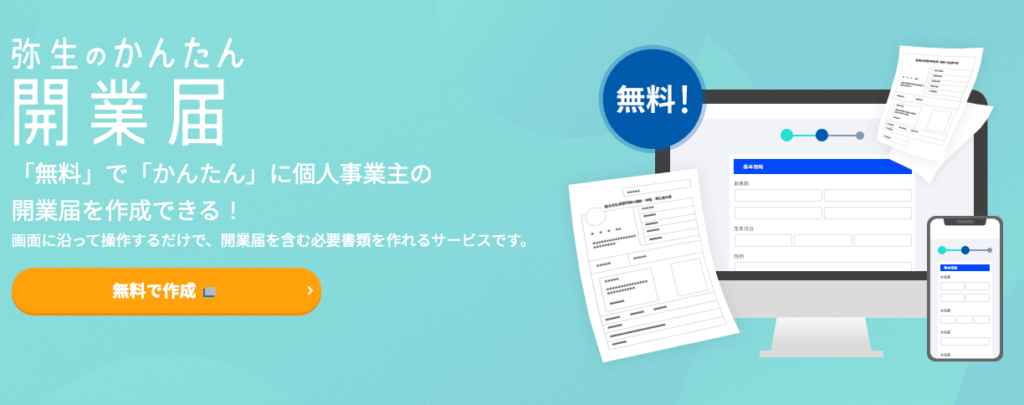
弥生のかんたん開業届は、会計ソフト「弥生」が提供している無料の開業届作成サービスです。
登録から書類の作成まで無料で利用することができて、画面の案内に従って必要項目を入力するだけで、開業届と青色申告承認申請書を同時に作成できます。
ステップに沿って必要な情報を入力していくだけなので簡単な操作で初心者でも理解しやすく、難しい専門知識を持たない人もスムーズに起業できます。
開業後も弥生会計との連携が可能で、開業後の会計業務もスムーズに移行できる点が魅力です。サポート体制も充実しており、電話やメールでの問い合わせにも対応しています。
■利用方法
- 弥生IDの新規登録
- 開業に必要な基本事項の入力
- 作成書類のダウンロード
- 税務署へ必要書類を提出
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 作成時間 | 約15分 |
| 操作性 | ★★★★★ |
| 作成書類 | 開業届・青色申告承認申請書 |
| サポート | 電話・メール |
| 会計ソフト連携 | 弥生会計 Next |
| スマホ対応 | あり |
freee開業

freee開業は、クラウド会計ソフト大手のfreeeが提供する開業手続き支援サービスです。
最大の特徴は、開業届の作成から提出まで完全オンラインで完結できることです。ステップバイステップの質問形式で必要情報を入力し、約5分で書類作成が完了します。作成される書類は開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、開業に必要な書類を網羅しています。
さらに、作成した書類はe-Taxを通じて電子申告も可能で、税務署に行く必要がありません。スマートフォン専用アプリもあり、移動中でも手続きができます。開業後はfreee会計やfreee人事労務といった他のサービスとの連携により、経理や労務管理も一元化できます。無料で利用でき、会計の知識がない方でも安心して開業手続きができる優れたツールです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 作成時間 | 約5分 |
| 操作性 | ★★★★☆ |
| 作成書類 | 開業届・青色申告承認申請書 給与支払事務所等開設届出書 |
| サポート | チャット・メール |
| 会計ソフト連携 | freee会計 |
| スマホ対応 | あり |
国税庁公式サイト
国税庁の公式サイトは、最も確実で信頼性の高い情報源として利用できます。
「確定申告書等作成コーナー」では、開業届や青色申告承認申請書を正確に作成できます。各項目の記入方法について詳細な説明があり、税務上の正しい知識を身につけながら書類作成ができます。e-Taxを利用すれば電子申告も可能で、24時間受付、即時受付通知、控えの電子保存などのメリットがあります。
さらに、開業に関するQ&Aや各種パンフレットも充実しており、開業手続きに関する疑問を解消しやすいです。費用は完全無料で、広告や誘導もないため安心して利用できます。ただし、操作に慣れるまで時間がかかる場合があり、初心者には少しハードルが高い面もあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 作成時間 | 約20分 |
| 操作性 | ★★☆☆☆ |
| 作成書類 | 全ての税務関連書類 |
| サポート | なし |
| 会計ソフト連携 | なし |
| スマホ対応 | あり |
副業版:開業届についてよくある質問(Q&A)
これから開業届を出そうと検討していても、何をどうすればいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。
- 副業が会社にバレないように開業届を出す方法はある?
- 収入が20万円未満でも開業届は必要?
- 開業届を出すとすぐに税金が増える?
- 屋号は必ずつける必要がある?
- 一度提出した開業届を取り消せる?
副業が会社にバレないように開業届を出す方法はあるの?
開業届の提出自体で副業が会社に直接バレることはありませんが、住民税の金額変化でバレる可能性はあります。
対策としては、確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付」(普通徴収)を選択することです。これにより副業分の住民税は自宅に納付書が送られ、会社の給与から天引きされません。ただし、市区町村によっては普通徴収を受け付けない場合もあるため、事前に確認が必要です。
また、開業届に記載する屋号は公開情報ではないため、屋号から副業がバレる心配はありません。それでも完全にリスクをゼロにすることは困難で、副業を行うときは会社の就業規則を確認し、必要に応じて事前相談することをおすすめします。
収入が20万円未満でも開業届は必要なの?
法律上、収入額に関わらず継続的に事業を行っている場合は開業届の提出が義務付けられています。
年間所得20万円未満で確定申告が不要であっても、開業届の提出義務は別の話です。ただし、実際には提出しなくても罰則はありません。しかし、将来的に収入が増える可能性がある場合や青色申告の準備をしておきたい場合は提出しておくメリットがあります。
青色申告承認申請書は開業から2か月以内(その年の3月15日まで)に提出する必要があるため、後から「提出しておけばよかった」と後悔することも。収入が少なくても事業として継続する意思があれば、早めの提出を検討しましょう。
開業届を出すとすぐに税金が増えるの?
開業届の提出自体で税金が増えることはありません。
税金は実際の所得に基づいて計算されるため、開業届の有無は直接影響しません。むしろ、開業届を提出して青色申告を選択すれば、65万円の特別控除により税負担を軽減できます。例えば、副業所得が100万円ある場合、青色申告特別控除を適用すれば課税所得は35万円となり、大幅な節税効果が期待できます。
また、事業所得として計上することで、パソコンや書籍代などの必要経費も差し引けるため、実質的な税負担は軽くなる場合が多いです。ただし、事業所得として申告する場合は適切な帳簿付けが必要になるため、記帳の手間は増加します。
屋号は必ずつける必要があるの?
屋号の設定は必須ではありません。
開業届の屋号欄は空欄のまま提出しても問題はなく、個人名で事業を行う場合は屋号なしでも全く支障がありません。屋号をつけるメリットとしては、事業用銀行口座を開設しやすくなる、請求書や名刺などでプロフェッショナルな印象を与えられる、事業とプライベートの区別が明確になるなどがあります。
一方、屋号をつけることで事業性が強調され、会社に副業がバレるリスクが若干高まる可能性もあります。屋号は後から変更も可能で、変更届を提出すれば新しい屋号に変更できます。事業の性質や将来の展望を考慮して、必要に応じて設定を検討しましょう。フリーランスや物販事業では屋号があると便利な場合が多いです。
一度提出した開業届を取り消せるの?
開業届自体を取り消すことはできませんが、事業を廃止する場合は「個人事業の廃業届出書」を提出が必要です。
これにより個人事業主を辞めることが可能です。廃業届は事業廃止から1か月以内に提出する必要があり、青色申告の適用も同時に取りやめられます。ただし、副業を完全にやめるのではなく、一時的に休止する場合は廃業届の提出は適切ではありません。
また、収入が減ったからといってすぐに廃業届を出す必要はなく、事業を継続する意思があれば開業届はそのままで問題ありません。廃業後に再び事業を始める場合は新たに開業届を提出する必要があります。将来の事業継続可能性を慎重に検討してから廃業の判断をすることをおすすめします。
副業をしている人が開業届けを出すメリット・デメリットのまとめ
ここまで、副業をしている人に向けて開業届を出すメリットやデメリットについて紹介をしてきました。
開業届の提出や毎年の確定申告をするは面倒ではありますが、経費の範囲が増えたり、最大で65万円の控除を受けることができます。
そのため課税所得額が減り、納める税金も減らす事が可能です。開業していない人に比べると、青色申告を選んだ方 方が差し引ける金額が多くなるため、節税効果が期待できます。
\開業届を提出するなら利用したいツール3選!/
 マネーフォワードクラウド開業届 |  freee開業 | 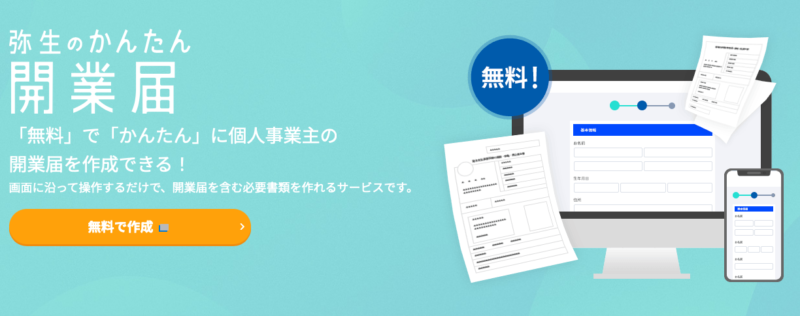 弥生のかんたん開業届 | |
|---|---|---|---|
| 作成時間 | 約10分 | 約5分 | 約15分 |
| 電子申告 | なし | あり | なし |
| 作成書類 | 開業届 青色申告承認申請書 | 開業届 青色申告承認申請書 給与支払事務所等開設届出書 | 開業届 青色申告承認申請書 |
| 会計ソフト連携 | マネーフォワード会計 | freee会計 | 弥生会計 |
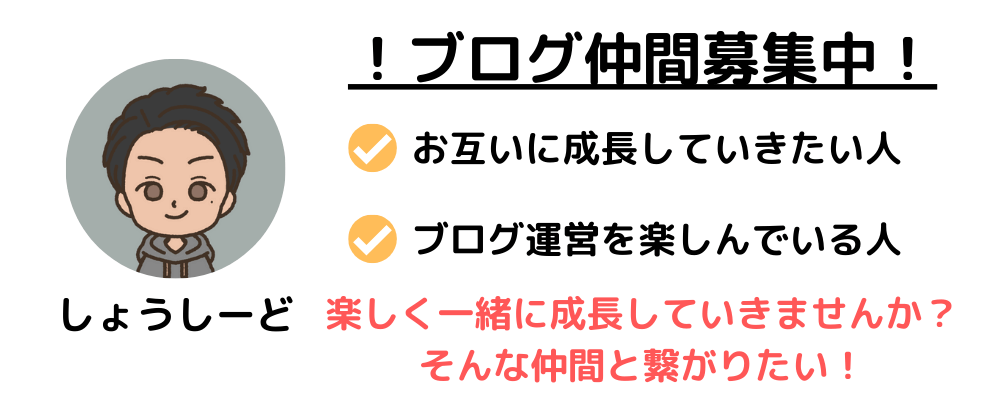
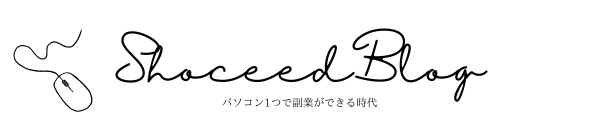


コメント