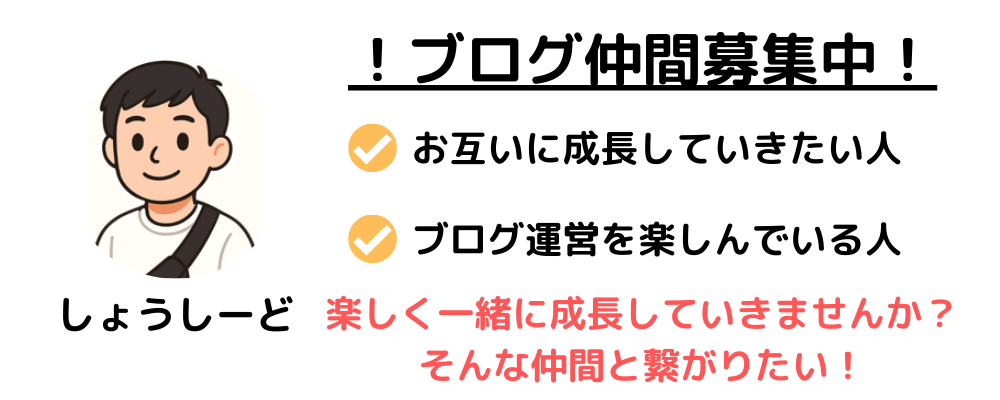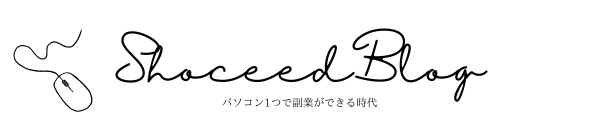「投資信託を始めたいけど、どのネット証券にすればいいかわからない」
「おすすめのネット証券会社があれば教えて欲しい」
投資信託をするには証券会社に登録をして、はじめる必要がありますが、どのネット証券会社にすればいいかわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、投資信託を始めるのにおすすめなネット証券会社を紹介します。投資信託をはじめるメリットやデメリット、注意点なども丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
■この記事は以下の内容が書かれています
- 投資信託におすすめのネット証券会社の紹介
- 投資信託を始めるメリット・デメリット
- 自分に合った証券会社を選ぶときのポイントや注意点
■この記事でわかること
- 投資信託をすぐに始めるための手順がわかりスムーズに始められる
- 投資信託の良さを理解でき、始めたほうがいいんだなと把握する
- ネット証券会社のメリットとデメリットが理解でき、自分に合っているか判断できる
それでは、早速スタートします!
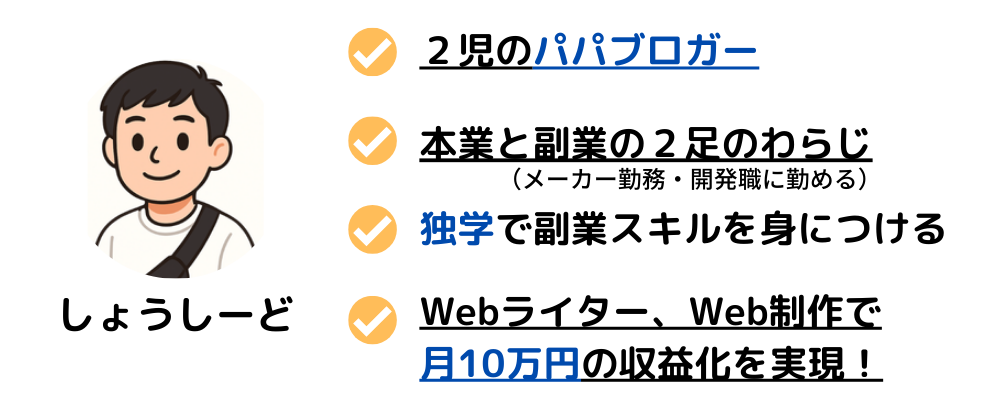
\投資信託を始めるなら利用したいネット証券会社3選!/
初心者にもわかりやすい投資信託の仕組みとは?
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金を一つにまとめて、投資のプロフェッショナルが株式や債券などに投資・運用する金融商品です。
その仕組みを身近な例で説明すると、友人同士でお金を出し合って高級レストランに行くようなイメージです。一人では高すぎて行けないレストランでも、みんなでお金を出し合えば利用できるように、投資信託では少額の資金しか持たない個人投資家でも、大きな資金が必要な投資に参加できます。
投資信託には主要な関係者が3つ存在します。
- 販売会社
証券会社や銀行などで、投資家が投資信託を購入する窓口 - 運用会社
実際にファンドの運用方針を決定し、投資判断を行う会社 - 信託銀行
投資家から集めたお金や購入した株式・債券などを安全に保管・管理する役割
この三者がそれぞれ独立してチェック機能を働かせることで、投資家の資産が守られる仕組みになっています。
投資信託の価格は「基準価額」と呼ばれ、通常1万口あたりの価格で表示されます。この価格は投資信託が保有する株式や債券の時価総額を、発行済みの口数で割って計算されます。株式市場が上がれば基準価額も上昇し、下がれば基準価額も下落するため、投資信託の価値は日々変動します。
投資信託は基準価額の変動により利益や損失が生まれ、長期的な値上がりや分配金によって利益を得ることができるのです。
投資信託を始めるメリット
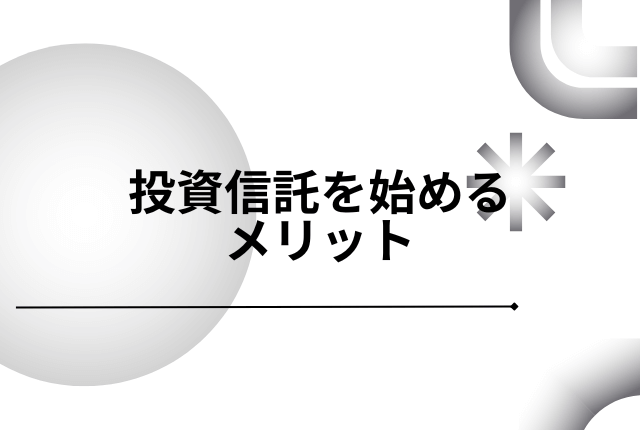
投資信託をはじめるときは、とても不安な方が多いのではないでしょうか。失敗してしまうリスクや何からすればいいのかわからないと悩んでしまいますよね。
投資信託をはじめるメリットとして、以下があります。
- 少額から始められる
- 運用はプロに任せられる
- 分散投資によるリスクを分散できる
まずは、どんなメリットがあるのは一緒に確認していきましょう。それぞれ、順番に解説をします。
少額から始められる
投資信託は、株と違ってまとまった資金がなくても投資が始められるます。
多くの証券会社では月々100円や1,000円といった少額から積立投資が可能で、学生やサラリーマンでも気軽にスタートできます。株式投資では一つの銘柄を購入するのに数万円から数十万円が必要な場合もありますが、投資信託なら小さな金額から様々な投資先に分散投資できるのです。
この仕組みにより、投資初心者でも無理のない範囲で資産形成を始めることができ、投資の勉強をしながら徐々に投資額を増やしていくことも可能です。
運用はプロに任せられる
投資信託では、ファンドマネージャーと呼ばれる投資のプロフェッショナルが資金の運用を行います。
投資初心者が企業の業績分析や経済情勢の把握をして、適切な売買タイミングを判断するのはとても難しいですが、投資信託なら豊富な知識と経験を持つ専門家に運用を委託できます。
ファンドマネージャーは市場動向を常に監視し、最適な投資判断を下すため、投資初心者でもプロレベルの運用の恩恵を受けられるのです。また、運用会社には調査チームやアナリストも在籍しており、個人では入手困難な情報も活用した運用をしてるれるので、マイナス運用になることも少ないです。
分散投資によるリスクを分散できる
投資信託は多数の投資家から集めた資金をひとつにまとめ、様々な株式や債券に分散投資を行います。
たとえば、一つの企業の株式だけに投資した場合、その企業の業績が悪化すると大きな損失を被る可能性がありますが、数十から数百の銘柄に分散投資していれば、一部の投資先で損失が出ても他の投資先でカバーできる可能性があります。
また、国内外の株式、債券、不動産など異なる資産に投資するファンドもあり、より幅広いリスク分散が可能です。この分散効果により、投資における損失リスクを抑えながら安定した運用成果を目指すことができるのです。
投資信託を始めるデメリット
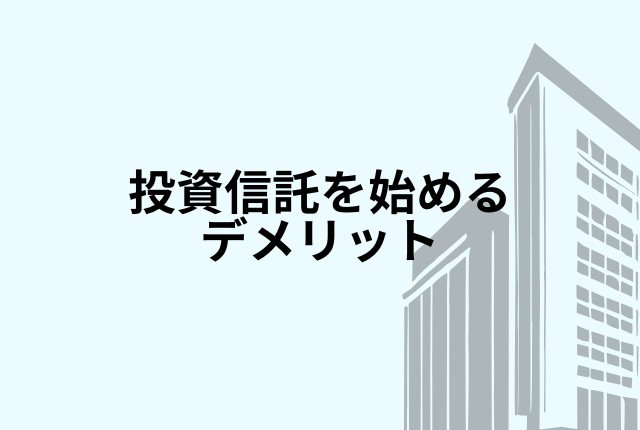
投資信託はたくさんのメリットがある一方で、デメリットも存在します。デメリットを知らないで投資信託を始めてしまうと、失敗してしまう可能性があるので、ここでしっかりと理解をしておきましょう。
- 元本割れする可能性がある
- 短期間で大きな利益を得にくい
- 手数料がかかる
それぞれ、順番に解説をします。
元本割れする可能性がある
投資信託は投資商品であるため、預金とは異なり元本保証がありません。
市場環境が悪化したり、投資先企業の業績不振などがあった場合は、投資した金額を下回る可能性があります。
株式型の投資信託では、株価の変動により短期間で大きく値下がりすることもあり得ます。リーマンショックやコロナ禍のような世界的な経済危機が発生した際には、多くの投資信託で大幅な下落が見られました。
誤った知識で、下落したときに大きな損失にならないように焦って売ってしまえば、それだけ損をしてしまいます。投資信託を始めるときは、この元本割れリスクを十分に理解し、売るタイミングを間違えない、資金は生活に支障のない余裕資金で行うことをおすすめします。
短期間で大きな利益を得にくい
投資信託は長期的な資産形成を目的とした商品であり、短期間で大きな利益を狙うギャンブル的な投資には向いていません。
分散投資によりリスクを抑えている分、個別株投資のような爆発的な値上がりは期待しにくいのが現実です。また、多くの投資信託は中長期的な成長を目指して運用されているため、数日や数週間といった短期間では目立った成果が現れにくい傾向があります。
「すぐにお金を増やしたい」という考えで投資信託を始めると、期待と現実のギャップに失望してしまう可能性があります。投資信託は時間をかけてじっくりと資産を育てる投資手法であることを知っておきましょう。
手数料がかかる
投資信託には様々な手数料が設定されており、これらのコストがかかることを理解しておきながら運用をしていかないと、運用成果に影響を与えます。
主な手数料として、購入時にかかる「販売手数料」、保有中に継続的にかかる「信託報酬(管理費用)」、解約時にかかる「信託財産留保額」があります。
特に信託報酬は保有している限り毎日差し引かれるため、長期投資では大きなコスト負担となる可能性があります。例えば、信託報酬が年率2%のファンドを10年間保有した場合、単純計算で元本の20%相当がコストとして差し引かれることになります。
手数料は投資信託選びの重要な判断材料であり、コストを抑えることが長期的な投資成果の向上につながります。
投資信託におすすめな証券会社TOP7
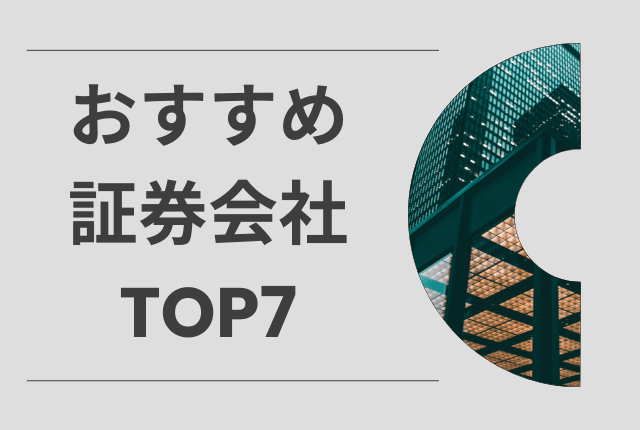
投資信託をはじめるならこれから紹介する7つのネット証券会社のなかから自分に適した証券会社を選んでみて下さい。
それぞれの証券会社の特徴や手数料、取り扱い本数を含めて比較してきますので、ぜひ参考にしてみてください。
楽天証券

楽天証券は、楽天グループの強みを活かした豊富なポイントサービスが最大の特徴で、NISA講座や満足度でNo.1を取得しています。
投資信託のラインナップも豊富で、取扱数は約2600本で業界でもトップクラス(2025年8月時点)となっており、すべての投資信託のすべての銘柄の買付手数料が無料です。楽天カードで積立投資を行うと最大2%のポイント還元を受けられ、さらに貯まった楽天ポイントで投資信託を購入することも可能です。
投資信託の保有残高に応じて楽天ポイントが貯まる「投信残高ポイントプログラム」もあり、長期保有するほどお得になります。スマートフォンアプリ「iSPEED」は直感的で使いやすく、初心者でも簡単に操作できます。一方で、ポイント還元率の改悪や楽天経済圏以外の利用者にはメリットが少ない点がデメリットとして挙げられます。楽天市場をよく利用する方には特におすすめの証券会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | 楽天証券 |
| 投資信託数 | 2,621本 |
| 米国株 | 5,100銘柄以上 |
| 株式売買手数料 | 無料 |
| ポイントサービス | 楽天ポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 277銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
SBI証券

SBI証券は国内最大手のネット証券として、投資信託の取扱本数が業界トップクラスの約2,600本以上を誇り、そのほとんどが購入手数料無料となっています。
SBI証券は「ゼロ革命」で国内株手数料が無料(条件を満たせば完全ゼロ)と、手数料面でも非常に競争力があります。VポイントやPontaポイント、dポイントなど複数のポイントサービスに対応しており、利用者の好みに合わせて選択できる柔軟性があります。
また、クレジットカード積立では三井住友カードを利用すると0.5〜5.0%のポイント還元が受けられ、積立投資でのポイント獲得効率が高いのも魅力です。取引ツールも豊富で、初心者向けから上級者向けまで幅広く用意されています。
デメリットとしては、サイトの情報量が多すぎて初心者には分かりにくい場合があることや、サポート体制が他社と比べてやや劣る点が挙げられます。総合力の高さで選ぶなら最有力候補です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | SBI証券 |
| 投資信託数 | 2,641本 |
| 米国株 | 4,950銘柄 |
| 株式売買手数料 | 無料 |
| ポイントサービス | Vポイント Pontaポイント dポイント PayPayポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 281銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
松井証券

松井証券は創業100年を超える老舗証券会社で、手厚いサポート体制が最大の強みです。
投資信託の取扱本数は約1,900本と他社より少なめですが、厳選された優良ファンドが揃っており、すべて購入手数料無料で投資できます。特筆すべきは、電話サポートの質の高さで、投資初心者にも丁寧に対応してくれると評判です。
また、AIチャットボットによる24時間サポートも充実しており、疑問点をすぐに解決できます。NISA口座での国内株式取引手数料が無料である点も魅力的です。投資信託の保有残高に応じて「松井証券ポイント」が貯まり、Amazonギフトカードなどに交換できます。
一方で、ポイント還元率が他社と比べて低めであることやクレジットカード積立に対応していない点がデメリットですが、投資初心者で手厚いサポートを重視する方には特におすすめです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | 松井証券 |
| 投資信託数 | 1,903本 |
| 米国株 | 4,900銘柄以上 |
| 株式売買手数料 | 〜50万円:無料 100万円:1,100円 |
| ポイントサービス | 松井証券ポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 273銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
三菱UFJeスマート証券
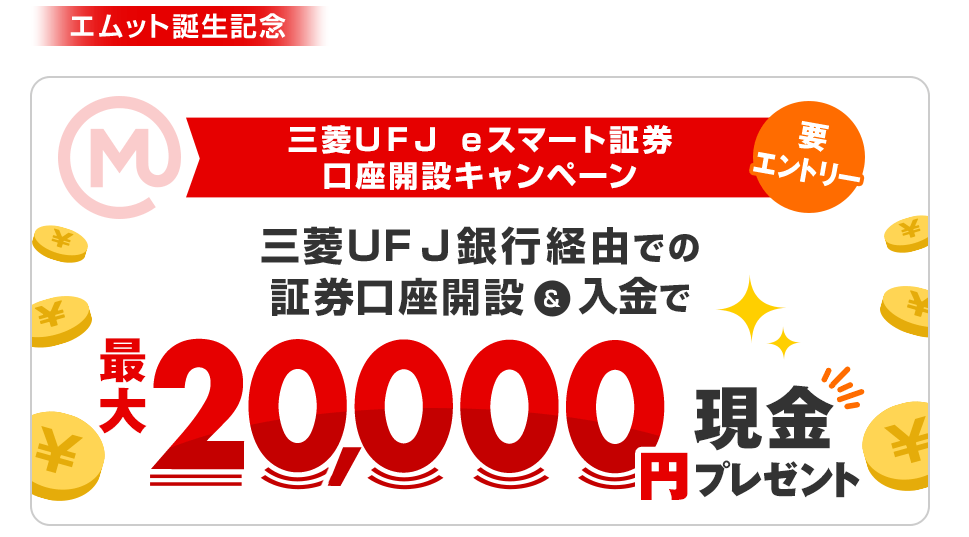
三菱UFJeスマート証券(旧auカブコム証券)は、三菱UFJフィナンシャル・グループとKDDIが共同出資する証券会社で、au経済圏との連携ができるのが特徴です。
投資信託の取扱本数は約1,800本で、すべて購入手数料無料となっています。最大の魅力は、auカブコムFXで投資信託を積立購入するとPontaポイントが最大5%還元される点です。また、25歳以下の方が国内株式の現物手数料が無料になる「U25割」など、若年層向けのサービスが充実しています。
auじぶん銀行との連携により、円普通預金金利が優遇される「auマネーコネクト」も利用できます。スマートフォンアプリは使いやすく、初心者でも簡単に操作可能です。デメリットとしては、au経済圏以外の利用者にはメリットが少ないことや、他社と比べて投資信託の取扱本数がやや少ない点が挙げられます。auユーザーや若年層には特にメリットの大きい証券会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | 三菱UFJeスマート証券 |
| 投資信託数 | 1,869本 |
| 米国株 | 1,950銘柄 |
| 株式売買手数料 | ◯1日定額 〜100万円:無料 ◯1約手定ごと 10万円:99円 20万円:115円 50万円:275円 |
| ポイントサービス | Pontaポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 265銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
マネックス証券

マネックス証券は、投資情報の充実度とグローバル投資への対応力が高いのが特徴の証券会社です。
投資信託の取扱本数は約1,800本で、すべて購入手数料無料となっています。最大の魅力は、マネックスカードで投資信託を積立購入すると1.1%のマネックスポイント還元が受けられることで、これは業界最高水準の還元率です。また、米国株や中国株の取扱銘柄数が豊富で、海外投資を重視する投資家には特におすすめです。
投資レポートや銘柄分析ツールが充実しており、投資判断に役立つ情報を多数提供しています。NISA口座での国内株式・ETF手数料が無料である点も魅力的です。国内株式の売買手数料が他社と比べて高めに設定されていることや取引ツールがやや複雑で初心者には難しい場合がある点がデメリットです。投資を本格的に学びたい方や海外投資に興味がある方におすすめの証券会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | マネックス証券 |
| 投資信託数 | 1,831本 |
| 米国株 | 5,000銘柄 |
| 株式売買手数料 | ◯1日定額 〜100万円:550円 ◯1約手定ごと 10万円:99円 20万円:115円 50万円:275円 |
| ポイントサービス | マネックスポイント dポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 272銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
GMOクリック証券

GMOクリック証券は、GMOインターネットグループが運営する証券会社で、シンプルで分かりやすいサービス体系が特徴です。
投資信託の取扱本数は約130本と他社と比べて少なめですが、厳選された低コストの優良インデックスファンドが中心となっており、初心者には選びやすい構成です。GMOクリック証券は信用取引ともに0円(完全無料)に引き下げ、投資信託やFX、CFDの取引手数料もすべて無料となっており、コスト面で非常に優れています。
また、GMOクリック証券独自の「GMOポイント」が貯まり、現金に交換できる点も魅力的です。取引画面がシンプルで見やすく、投資初心者でも迷わずに操作できます。一方で、投資信託の選択肢が限られることや、ポイント還元率が他社と比べて低い点、サポート体制がやや手薄な点がデメリットです。シンプルで低コストな投資を求める方や、選択肢が多すぎると迷ってしまう初心者におすすめです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | GMOクリック証券 |
| 投資信託数 | 155本 |
| 米国株 | 118銘柄 |
| 株式売買手数料 | 無料 |
| ポイントサービス | ー |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 43銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
SMBC日興証券

SMBC日興証券は、三井住友フィナンシャルグループの大手総合証券会社で、豊富な投資情報と手厚いサポート体制が特徴です。
投資信託の取扱本数は約1,000本で、購入手数料無料のファンドも多数揃っています。最大の魅力は、投資信託の保有残高に応じて「dポイント」が貯まる「dポイントプログラム」で、年率最大0.2%のポイント還元が受けられます。また、投資レポートやマーケット情報が非常に充実しており、プロのアナリストによる質の高い情報を無料で利用できます。
店舗も全国にあるため、対面でのサポートを受けることも可能です。NISA口座での国内株式売買手数料が無料である点も魅力的です。一方で、ネット証券と比べて売買手数料が高めに設定されていることや、取引ツールの使い勝手がやや劣る点がデメリットです。投資情報を重視する方や、店舗での相談も利用したい方におすすめの証券会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 証券会社名 | SMBC日興証券 |
| 投資信託数 | 1,057本 |
| 米国株 | 2,300銘柄 |
| 株式売買手数料 | ◯1日定額 〜100万円:無料 ◯1約手定ごと 10万円:88円 20万円:100円 50万円:198円 |
| ポイントサービス | dポイント |
| NISA(つみたて投資枠取扱銘柄数) | 157銘柄 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
投資信託で証券会社を選ぶときの5つのポイント
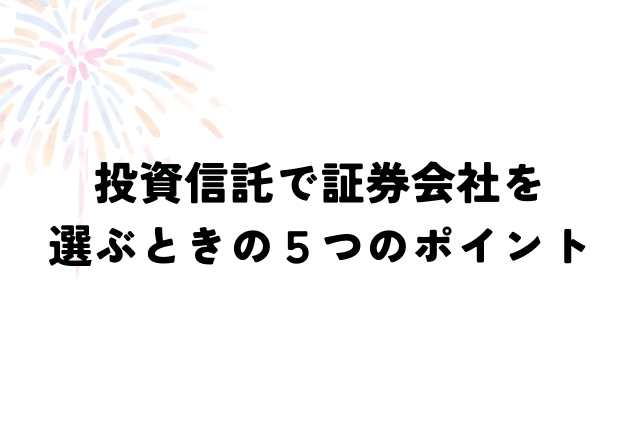
はじめて投資信託をするときに何を基準に証券会社を選べばいいのか悩みますよね。ここでは、証券会社を選ぶときの5つのポイントについて解説します。
- 取り扱い本数の多さ
- 手数料の低さ
- 少額積立ができる
- ポイントサービスがあるか
- ツールの使いやすさやサポート体制が充実しているか
それぞれ、順番に解説していきます。
取り扱い本数の多さ
証券会社選びでは、投資信託の取り扱い本数が多いところを選びましょう。
大手ネット証券では2,000本以上のファンドを取り扱う一方、地方銀行などでは数十本程度しか取り扱っていないことが多いです。取り扱い本数が多いということは、それだけ多様な投資戦略や運用方針から自分に合ったファンドを選べるということです。
たとえば、新興国株式、高配当株式、インデックスファンド、テーマ型ファンドなど、様々な投資方針のファンドが揃っていれば、投資スタイルの変化や市場環境の変化に応じて柔軟にポートフォリオを調整できます。
また、優良な低コストファンドの取り扱いがあるかも確認ポイントです。将来的な投資の幅を広げるためにも、豊富な選択肢を提供する証券会社を選ぶことが賢明です。
手数料の低さ
投資信託における手数料は、長期的な投資成果に大きな影響を与えるため、可能な限り低コストの証券会社を選びましょう。
主要なネット証券では、多くの投資信託で購入手数料を無料(ノーロード)にしており、これだけで年間数万円のコスト削減につながる場合もあります。また、同じファンドでも証券会社によって購入手数料が異なるケースがあるため、必ず比較をして下さい。
さらに、NISA口座での取引手数料や、積立投資の手数料体系も確認しましょう。一部の証券会社では、保有残高に応じてポイント還元を行っており、実質的な手数料負担を軽減できます。
手数料1%の差が20年後には数十万円の差となって現れることもあるため、初期の証券会社選びでしっかりと比較することが大切です。
少額積立ができる
投資初心者にとって、少額から積立投資を始められるかどうかは投資をはじめる上での重要な判断基準のひとつです。
多くのネット証券では月100円から積立設定が可能で、学生やお小遣いが少ない方でも無理なく投資を始められます。少額積立のメリットは、リスクを抑えながら投資の経験を積めることと、ドルコスト平均法による価格変動リスクの軽減効果が期待できることです。
また、家計への負担が少ないため、長期間継続しやすく、時間を味方につけた資産形成が可能になります。積立頻度についても、毎月だけでなく毎週や毎日積立に対応している証券会社もあり、より細かく分散投資ができます。将来的に投資額を増やしていくときにも、最初から少額積立に慣れ親しんでおくことで、スムーズに投資規模を拡大していけるでしょう。
ポイントサービスがあるか
以下のネット証券会社では、投資信託の保有残高や積立金額に応じてポイントが貯まるサービスを提供しています。
- 楽天証券→楽天ポイント
- SBI証券→VポイントやPontaポイント
- マネックス証券→dポイントなど
- 松井証券→Oki Dokiポイント
貯まったポイントは投資信託の購入代金に充てることや何か欲しいものを購入するときに役立ちます。
年間数千円から数万円相当のポイントが貯まることもあり、実質的な利回り向上効果が期待できます。また、貯まったポイントで追加投資を行えば、元手ゼロで投資元本を増やすことができ、複利効果をより高めることができます。さらに、クレジットカード決済で積立投資を行える証券会社では、カードのポイント還元も同時に受けられるため、二重でお得になります。
ポイントサービスは証券会社選びの決定打にはなりませんが、長期投資では無視できないメリットとなるでしょう。
ツールの使いやすさやサポート体制が充実しているか
投資信託を長期間保有していくうえで、証券会社の取引ツールの使いやすさとサポート体制が整っていないと運用が面倒になり長続きしません。とくに確認しておきたいことが、以下の項目です。
- スマートフォンアプリが直感的に操作できる
- 資産状況の確認や積立設定の変更が簡単におこなえる
- ファンドの検索機能や比較機能が充実している
- 分析ツールやレポート機能がある
検索機能や分析ツールなどは投資の勉強に役立ちますので機能としてあるか確認をしましょう。サポート体制では、電話やチャット、メールでの問い合わせ対応時間や投資初心者向けのセミナーや情報提供サービスの有無も確認ポイントです。
特に投資を始めたばかりの頃は分からないことが多いため、丁寧なサポートを受けられる証券会社を選ぶと安心して投資を続けられるでしょう。
- マネックス証券

保有で「マネックスポイント」が貯まり、Amazonギフト券や暗号資産に交換可能。100円から、毎日・月1回、ボーナス月設定もできます。 - GMOクリック証券
銘柄はあえて厳選(約116本)し、初心者にも選びやすい設計がされています。低コストインデックス・アクティブファンドあり! - SMBC日興証券
安心感のある大手証券ならではの信頼性とサポートが充実。多様なテーマ型・高配当・長期投資向けファンドなど豊富な品揃えが魅力! - 三菱UFJ eスマート証券
auカブコムFXで投資信託を積立購入するとPontaポイントが最大5%還元!25歳以下は国内株式の現物手数料が無料になる「U25割」など、若年層向けのサービスが充実。
投資信託をスムーズに始まるための4ステップ
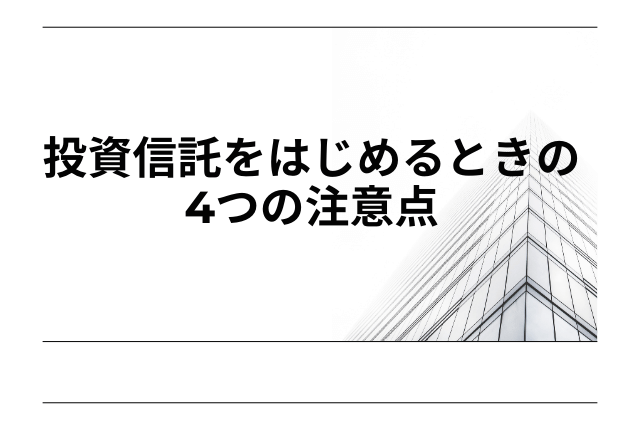
いざ、投資信託を始めようと思っても何から手をつければいいのかわからないですよね。ここでは、そんな悩みを解決すべく投資信託をはじめるための4ステップをご紹介します。
- ステップ1:証券会社に口座を開設する
- ステップ2:自分に合ったファンドを選ぶ
- ステップ3:少額の積立設定をおこなう
- ステップ4:定期的に資産状況をチェックする
それぞれ、順番に解説をしていきます。
ステップ1:証券会社に口座を開設する
投資信託を始める第一歩は、証券会社での口座開設です。現在はオンラインで手続きが完結するため、平日に窓口に行く必要はありません。
口座を開設するときに必要な書類を準備します。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード
口座開設時には、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、税務処理が自動化されて便利です。また、NISA口座の同時開設も検討しましょう。NISAを利用すれば、年間一定額までの投資で得た利益が非課税になるため、税務上のメリットが大きいです。
口座開設には通常1〜2週間程度かかりますが、最近は最短翌営業日から取引開始できる証券会社も増えています。開設完了後は、ログイン情報を安全に管理し、初回ログイン時にはセキュリティ設定も確認しておきましょう。
ステップ2:自分に合ったファンドを選ぶ
口座の開設が完了したら次におこなうのは、自分に合ったファンド選びをしましょう。
まず、自分の投資目的(老後資金、教育資金、短期的な資産増加など)と投資期間を明確にしましょう。長期投資なら株式中心のファンド、安定性を重視するなら債券中心やバランス型ファンドが適しています。投資初心者には、世界中の株式に分散投資する全世界株式インデックスファンドや国内外の株式と債券をバランス良く組み合わせたバランスファンドがおすすめです。
ファンド選びでは、信託報酬が年率0.5%以下の低コストファンドを中心に検討し、運用実績や純資産総額もチェックしましょう。また、同じような投資対象のファンドでも運用会社によって特色が異なるため、目論見書で運用方針をしっかり確認することが大切です。
ステップ3:少額の積立設定をおこなう
ファンドを選んだら、実際に積立投資の設定を行いましょう。最初は月1,000円から5,000円程度の少額から始めることをおすすめします。
少額なら家計への負担も軽く、市場の値動きの傾向を勉強しながら投資経験を積むことができます。積立日は給料日直後に設定すると、自動的に投資資金を確保できて便利です。多くの証券会社では、積立金額の変更やボーナス時の増額設定も簡単に行えます。
積立投資のメリットは、ドルコスト平均法により購入価格が平均化されることと、相場の上下に関係なく定期的に投資を継続できることです。慣れてきたら徐々に積立金額を増やしていけば良いので、まずは無理のない金額で投資習慣を身につけることから始めましょう。設定完了後は、積立が正常に実行されているか初回の引き落とし後に確認しておきましょう。
ステップ4:定期的に資産状況をチェックする
投資先を決めて、積み立て投資を始めたあとは、定期的に資産状況をチェックする習慣をつけましょう。ただし、毎日のように値動きを確認する必要はありません。
月に1回程度、資産残高や運用成績を確認し、投資計画に沿って順調に進んでいるかをチェックしましょう。確認すべきポイントは、積立投資が正常に実行されているか、ファンドの基準価額の推移、トータルリターン(投資元本に対する損益の割合)などです。
また、半年や1年に一度は、当初の投資目標と現在の状況を照らし合わせ、必要に応じてポートフォリオの見直しを検討します。市場環境が大きく変化した場合やライフステージの変化(結婚、出産、転職など)があった場合には、投資方針の調整も必要になるかもしれません。
重要なのは、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で資産形成を続けることです。
投資信託を始めるときの4つの注意点
投資信託をはじめるときは、以下4つに注意しておく必要があります。
- 短期間で成果を求めない
- 手数料や信託報酬が高すぎないか確認する
- ひとつの国や業種に偏らないように分散投資を意識する
- 生活費は別で確保して無理のない資金でおこなう
それぞれ、順番に解説をしていきます。
短期間で成果を求めない
投資信託による資産形成は、長期的な視点で取り組んでいきましょう。
株式市場は日々変動するため、短期間では投資元本を下回ることも珍しくありません。しかし、過去の実績を見ると、10年や20年といった長期間では、経済成長に伴い投資成果がプラスになる可能性が高まる傾向があります。短期的な値動きに一喜一憂せず、時間を味方につけてじっくりと投資をしていきます。
また、毎月一定額を積み立て価格が低いときに購入数量が多くなり、価格が少ないときには少なくなる「ドルコスト平均法」を活用することで、価格変動リスクを軽減しながら安定した投資を続けることができます。焦らず、じっくりと資産形成に取り組むことが投資信託で成功するポイントです。
手数料や信託報酬が高すぎないか確認する
投資信託を選ぶは、手数料の水準を必ずチェックしましょう。
同じような投資対象であっても、ファンドによって手数料には大きな差があります。一般的に、販売手数料は0〜3%程度、信託報酬は年率0.1〜2%程度と幅があります。特に長期投資では、信託報酬のわずかな違いが将来的に大きな差となって現れます。近年はインデックスファンドなど低コストの商品も増えており、信託報酬が年率0.2%以下の優良ファンドも多数あります。
手数料が高いファンドが必ずしも高いリターンをもたらすとは限らないため、コストパフォーマンスを重視した選択が賢明です。手数料情報は目論見書や証券会社のサイトで確認できます。
ひとつの国や業種に偏らないように分散投資を意識する
投資信託を選ぶときは、投資対象が特定の国や業種に偏りすぎていないかを確認して、バランスよく購入するようにしましょう。
たとえば、日本株式のみに投資するファンドだけを保有していると、日本経済の低迷時には大きな影響を受けてしまいます。また、IT関連企業のみに投資するファンドでは、その業界に固有のリスクが集中してしまいます。
理想的なポートフォリオは、国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)など、異なる資産範囲や地域に分散されたものです。世界全体の株式市場に投資する全世界株式インデックスファンドや株式と債券をバランス良く組み合わせたバランスファンドなども、分散投資の観点から良い選択肢となります。
生活費は別で確保して無理のない資金でおこなう
投資信託は元本割れの可能性がある商品であるため、生活に必要な資金とは明確に分けて考える必要があります。
家賃や食費、光熱費などの基本的な生活費、および緊急時に備えた資金(一般的に生活費の3〜6ヶ月分)は預金などの安全な方法で確保しておきましょう。投資に回すのは、これらの必要資金を除いた余裕資金のみとすることが鉄則です。無理をして生活費まで投資に回してしまうと、急な出費が必要になった際に投資信託を不利なタイミングで解約せざるを得なくなる可能性があります。
また、精神的な余裕がないと短期的な値動きに動揺してしまい、冷静な判断ができなくなるリスクもあります。自分の収入と支出を把握し、無理のない範囲で投資を行いましょう。
投資信託初心者が知っておくと役立つ情報
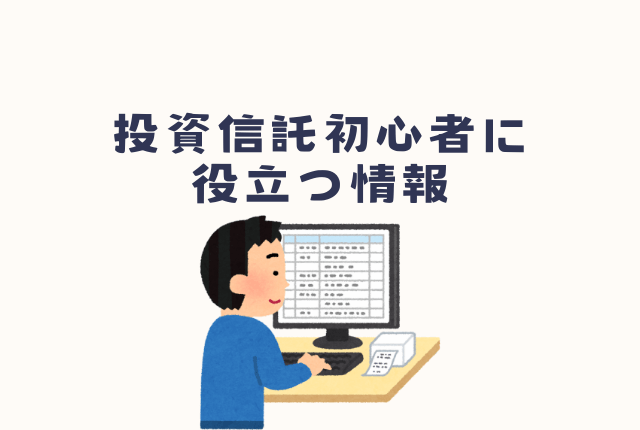
投資信託をはじめる前に知っておいた方がいい情報紹介します。
- 新NISA制度の活用する
- 投資信託の種類を把握する
- 資産配分の考え方を理解する
情報は投資をするうえで、成果に左右する重要なものです。成果の出る投資判断ができるようにここで紹介する役立つ情報は理解をしておきましょう。
新NISA制度の活用する
2024年1月から開始された新NISA制度は、投資信託を始める際に必ず活用すべき制度です。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | 1,200万円 |
| 投資対象商品 | 長期積立・分散投資に適した 投資信託 | 上場株式 投資信託 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
新NISAでは年間投資枠が大幅に拡大され、つみたて投資枠が年120万円、成長投資枠が年240万円で合計360万円まで投資可能になりました。また、生涯投資枠は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)に設定されています。
最大のメリットは、NISA口座で購入した投資信託から得られる利益(値上がり益や分配金)がすべて非課税になることです。通常であれば利益の約20%が税金として差し引かれますが、NISA口座なら丸々受け取れます。さらに、非課税保有期間が無期限になったため、長期間の資産形成に最適です。
売却した場合は翌年に投資枠が復活するため、柔軟な運用が可能になりました。投資信託を始める際は、まずNISA口座を開設することを強くおすすめします。
投資信託の種類を把握する
投資信託には様々な種類があり、それぞれ異なる特徴とリスク・リターンの関係を持っています。まず投資対象による分類としては以下です。
- 株式型(国内株式、先進国株式、新興国株式)
- 債券型(国内債券、外国債券)
- 不動産投資信託(REIT)
- 金など)
株式型は値動きが大きくリスクは高めですが、長期的には高いリターンが期待できます。債券型は値動きが比較的安定しており、安全性を重視する方に適しています。運用方法による分類では、市場平均に連動するインデックスファンドと、市場平均を上回ることを目指すアクティブファンドがあります。
一般的にインデックスファンドの方が手数料が安く、初心者には理解しやすいのでおすすめです。また、複数の資産に分散投資するバランスファンドもあり、一つのファンドで幅広い分散投資ができるため、ファンド選びに迷う初心者に人気です。
資産配分の考え方を理解する
資産配分は、投資の成果を左右する最も重要な要素のひとつです。これは、株式、債券、不動産など異なる資産投資にどのような比率で投資するかを決めることです。
一般的に「100マイナス年齢」の法則があり、たとえば30歳なら株式70%、債券30%といった配分が目安とされています。若いうちはリスクを取れるため株式の比率を高め、年齢を重ねるにつれて安定性の高い債券の比率を増やすという考え方です。
また、投資目的や期間によっても配分は変わります。老後資金のような長期目標なら株式中心、数年後の住宅購入資金なら債券中心にするなど、目的に応じて調整しましょう。さらに、地域分散も重要で、日本だけでなく先進国や新興国にも投資することで、一つの国の経済状況に左右されにくくなります。
初心者の場合は、世界分散投資ができるバランスファンドから始めるのも良い選択です。
投資信託は初心者でも少額から始めれて長期運用を心がけよう!
投資信託は株や不動産とは違い、少ない資金で始めることができ多くの知識がなくてもプロに運用を任せられる初心者向けの投資です。
ただ、知識がない状態で投資信託を始めるのはとても危険です。ここで解説した投資信託の仕組みやメリット・デメリットを理解して、損をしないように知識を身につけておきましょう。
\投資信託を始めるなら利用したいネット証券会社3選!/